【無明の闇】死んだらどうなるか分からない心
無明の闇(むみょうのやみ)
「無明の闇」の「無明」とは、「明かりが無い、暗い心」をいいます。
「闇」も同じく、「暗い」という意味です。
言葉を重ねて、心が暗いことが表されています。
この「暗い」とは、分からない、ハッキリしない、ということです。
例えば、「引っ越しをしたばかりなので、この辺りの地理に暗い」と言えば、どこにスーパーや郵便局などがあるのか、よく分からないということです。
ほかにも、パソコンに暗い、歴史に暗い、などと使われます。
では、仏教でいわれる「無明の闇」とは、何に暗い心なのでしょうか。
それは、死んだらどうなるのか分からない、死後がハッキリしない、ということであり、「死後が暗い心」のことをいいます。
「死後はない」と言いながら……
科学が発達した現代では、「死んだ後の世界なんてない。死んだら終わり」と言う人が多いかもしれません。
しかし、そんな人でも、いざ、友人や知人が亡くなると、無になったとは思えず、「ご冥福を、お祈りします」という気持ちが起こってくるのではないでしょうか。
「冥福」とは「冥土の幸福」を略した言葉です。
冥土とは、死後の世界のことです。
つまり、「冥福を祈る」とは、「死後の世界での幸せを祈る」という意味であり、死んだ後の世界を認めていることになります。
また、亡くなった人の命日やお盆に、墓参りをすることがあります。これも、先祖が墓の下にいると思うからこそ、やっていることですから、死後の世界を認めていることになります。
哲学者の池田晶子は、「死後はない」と言いながら、実際には、死後の世界があることを前提とした発言をしている人が多いことを、次のように指摘しています。
現代文明は、ほぼ唯物論の文明ですから、「公式見解」としては、多くの人は、死後の世界を信じていません。
(中略)
しかし、「死ねばなくなる」派の人でも、そのことが正確に何を言っているのか、自分で理解していないことに気がついていないことが多い。日常の会話や言い回しの端々に、じつはそうとは思っていないことが見てとれることが多い。
たとえば人は、「今度生まれ変わるとしたら」と、平気で言いますよね。あるいは「死んだ母が守ってくれる」、もしくは「向こうでお会いしましょうね」等々、死後の世界を想定しているのでなければあり得ない言い方を、人は大変よくします。もし「死ねば何もなくなる」と本当に思っているのだったら、日常会話からその種の言い回しは消滅しているはずではないのか。
『暮らしの哲学』池田晶子(著)
さらに、池田晶子は、「死」の怖さの本質を、次のように分析しています。
人は「無になる」ことを恐れているのではなくて、「わからない」ことを恐れているのです。死んだらどうなるかわからない、本当はこのことが怖いのです。
(『暮らしの哲学』より)
(『月刊 人生の目的』令和7年11月号より一部抜粋)
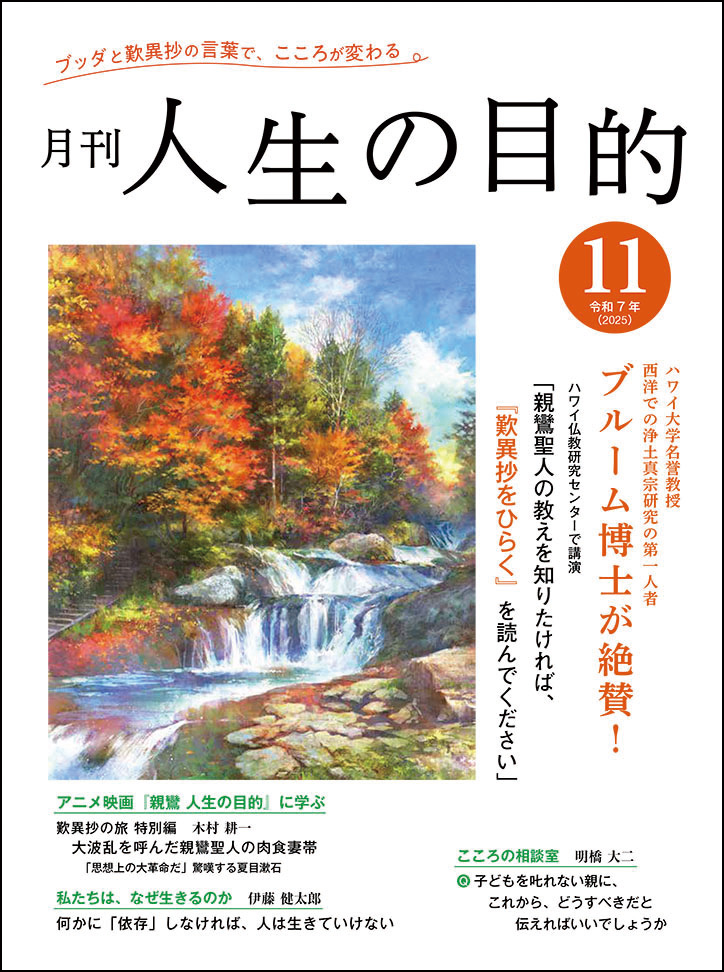
80ページ/A4変型
定価:700円(税込)
続きの主な内容
・「無明の闇」こそ苦しみの根元
・この世も未来も幸せに
②南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)
・この世も未来も完全に救い切る働き
・無明業障の恐ろしき病
③三業(さんごう)
・体と口と心の三つの行い
・なぜ「心の行い」を重視するのか
・罪の重さは、どうやって決まるのか
全文は本誌をごらんください。
『月刊 人生の目的』は書店ではお求めになれません。
ネットショップまたはお電話にて、ご注文ください。
単品注文は、税込1万円未満の場合は送料350円となります。
定期購読は送料無料でお得です。


